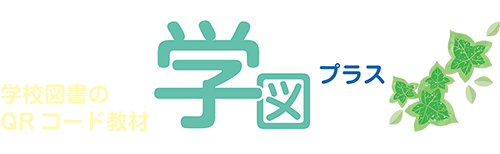氷の上で物体が滑りやすくなる理由について,たとえばスケートでは,靴のエッジによって高い圧力や摩擦が生じ,氷の表面がとけて薄い水の層ができているから…のような説明を聞いたことはないでしょうか。この説明は直感的でわかりやすいものですが,実際にくわしく調べると,表層で水がとけない-30℃以下のような低温であっても,氷の上では滑りやすいことが確認されます。そのため,本当の原因は,実は不明なままでした。
北京大学による最新の研究によって,氷の表面には,低温でも液体の水のようにふるまう分子が存在することが判明しました。この成果により,かつてファラデーが提唱した「氷表面の水分子層」の存在が正しかったことが証明され,圧力説や摩擦説だけでは説明できないことが改めて明らかになったのです。研究者たちは原子間力顕微鏡を用いて,-123℃の氷の表面を精査し,氷の結晶構造中に無秩序な水分子のようにふるまう層が存在することを確認しました。この分子層こそが,氷を滑りやすくする要因だったのです。さらに温度が上昇すると,この無秩序な層が広がり,氷の全面をおおうようになることもわかりました。今回確認されたこの特殊なふるまいをする水分子の層は「準液体層」とよばれ,氷の滑りやすさは,この準液体層の分子構造によるものであることが判明しました。
今回の事例は,きわめてシンプルにもかかわらず,これまでの理論では説明しきれなかった現象に光を当てた研究として高い価値があるといえます。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)