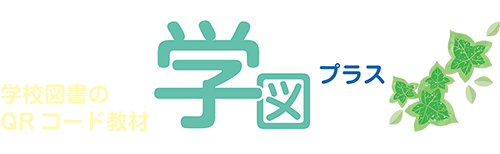“地球は青かった”
――これは,1961年にソ連(現ロシア)の宇宙飛行士ガガーリンが発した,有名な言葉です。ただしこの言葉は,より正確に補うなら,
“(地球は非常に長い地質年代の間,緑色の時代が続いていたが,いま現在宇宙から見るぶんには)地球は青かった” が正しいのかもしれません。
これまで,地球の海は『青い』ものと認識されてきましたが,名古屋大学を中心とした研究チームによって,太古代には緑色だった可能性が示されています。
約40億~25億年前には,海水中にはFe2+が豊富に存在し,還元的な海洋環境が続いていました。しかし,約30億年前からは光合成を行う生物が酸素を放出しはじめ,海中の鉄は酸化されてFe3+の微粒子となりました。この粒子は,青色~紫外線の波長の光を吸収しやすい性質があるため,結果として,海中では深海まで緑色の光が届く『緑の海』ができたと考えられています。このような環境の変化は,近年の地層の分析によって確かめられています。
この海洋環境では,緑色の光を効率よく利用できる生物が有利なため,光合成を行う微生物の一種であるシアノバクテリアがもつ,フィコビリンという色素が重要な役割を果たしていたと考えられます。フィコビリン系の色素は,緑色の光をよく吸収できることがわかっているからです。研究チームは,まず数値シミュレーションや培養実験を行い,フィコビリン系色素をもつ個体群が緑色光下で有利に繁殖することを確認しました。研究ではさらに,薩南諸島・硫黄島近海で,類似環境の実地調査も行っています。調査では,酸化鉄の粒子の影響で,緑色の光が届きやすい水域が存在し,この水域ではフィコビリン系の色素をもつシアノバクテリアが生息に適していることが判明しました。
この研究は,海洋環境と生物の相互作用を明らかにし,地質学的な大変動の裏づけに加え,さらには地球外生命体の探査にも新たな視点を提供しうる,重要なものといえます。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)