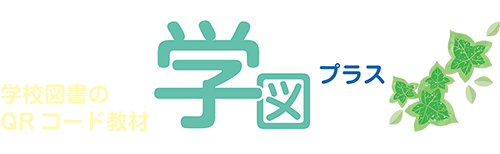「液体を加熱するときは,安全のため,必ず沸とう石を入れて加熱します。」
「コーラにメントスを入れると,大量の泡が一気にふき出します。」
一見すると無関係なこの2つの事例は,実は密接に関係しています。
まず,液体の加熱のときに沸とう石を使う理由を考えていきましょう。沸とう石は,特別な材質ではなく,素焼きのかけらやガラスなどが使用されています。これらの物体には,表面に無数の小さな孔(あな)が開いているという共通点があり,このような物体を多孔質といいます。多孔質の孔にふくまれる空気は,液体中でごく小さな気泡となり,液体の温度が沸点まで上昇したときに,液体の中で発泡をうながす核としてはたらきます。つまり,沸とう石が入っていることで,加熱された液体はスムーズに沸とうを起こすことができるのです。逆に,発泡の核となるものがほとんどふくまれていないようなときには,液体の温度は沸点を超えて上昇し,過加熱とよばれる状態になることがあります。この状態で,たとえば液体に衝撃が加わったり,核となる小さな気泡が液体中に生じたりすると,一気に沸とうが起こります。こうなると,沸点以上に加熱された熱い液体を周囲に激しくまき散らすことがあり,非常に危険です。これを防ぐため,教科書には,液体を加熱する際には必ず沸とう石を入れるように注意書きが載っています。
一方,コーラにメントスを入れると泡がふき出す,“メントスコーラ”とよばれる現象はどのように起こるのでしょうか。実はメントスを電子顕微鏡で見ると,表面にごく小さな孔が観察でき,多孔質としてはたらくことがわかります。そのため,沸とう石のしくみと同じように,メントスの孔にふくまれる空気は,コーラに入ると小さな気泡となり,泡の生成をうながす核としてはたらきます。この泡の生成が一気に起こるため,コーラからはまるで噴水のように大量の泡がふき出すこととなるのです。つまり,コーラに多孔質が入りさえすれば条件を満たすため,沸とう石をコーラに入れても,メントスのように多量の泡がふき出します。このようなしくみで起こっているため,メントスコーラ現象は,メントスとコーラにふくまれる物質の化学反応であるという理解は,一般には誤りといえます。ただし,他の炭酸飲料やキャンディを組み合わせても,メントス×コーラほどの発泡は起こらないため,ふくまれる合成甘味料が化学的にはたらいているという考察もなされているようです。
実験で沸とう石を扱うときには,ふき上がるコーラの泡に思いを馳せてみるのもよいかもしれません。