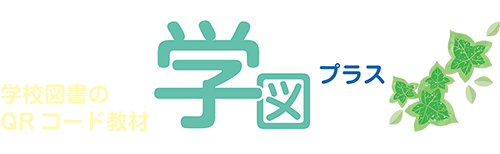毎年春先になると,コンクリートの上で赤色をした小さなダニを目にしたことがある人も多いかと思います。ぱっと目につくくらいに派手な赤色をしており,捕食者に見つけられやすいデメリットが大きそうですが,この体色にはどのような意味があるのでしょうか?
この真っ赤なダニはカベアナタカラダニという種類で,日本をふくむ北半球の広範囲に分布し,体長1mm前後の微生物です。このダニは,幼虫から成虫まで花粉を主食としていることがわかっています。今回,法政大学と京都大学が行った研究によると,赤色の原因は,えさとなる花粉から生成される,抗酸化作用を持つ色素であるカロテノイド,特にアスタキサンチンであることが判明しました。カベアナタカラダニは,春先に発生し,おもにコンクリートなどの人工物の上でくらしており,梅雨のころに卵を産んで次の春まで卵で過ごします。したがって,春先の紫外線を強く受ける環境で生きていく必要があります。紫外線による生物への悪影響としては,体内で有害な活性酸素が発生することがあげられますが,アスタキサンチンは高い抗酸化能力を備えており,この色素は酸化ストレスから身を守るのに役立つことが明らかとなりました。ちなみに,からだをつくるタンパク質あたりのアスタキサンチン量は,現在知られている微小な節足動物のなかで最も高く,2位の127倍というとんでもない赤さとなっています。
しかし同時に,冒頭にも書いたように,派手な赤色が捕食者に見つかりやすくなる可能性が考えられますが,この点は大丈夫なのでしょうか? 実は,このダニの天敵となるアリやカメムシは,眼の構造上,赤色を識別できないため,生存に不利な影響は少ないと考えられています。
このように,一見するとデメリットになりそうなド派手な赤色は,ダニにとって不利益をもたらさず,体内環境を守る有効な『鎧』として機能していることがわかったのです。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)