「化石」と聞くと,恐竜や哺乳類の大きな骨をイメージすることが多いかと思いますが,生物それ自体ではなくとも,その場所に生息していた生物のくらしのあとも立派な化石となります(1学年教科書p.170図13)。生物のくらしていた痕跡が残って化石となったものを,特に生痕化石といいます。
地中でくらすゴカイのなかまは,その生息場所に管状の空間(巣穴)をつくります。この空間が生痕化石となることが知られており,この生痕化石は,特にTerebellinaとよばれます。形状は直線〜曲線の細長い管状で,内部には細粒砂が充填されているのが特徴です。このTerebellinaが,鹿児島県屋久島の四万十累層群から,保存状態がよく,まとまった状態で発見されました。この生痕化石を手がかりに,当時の環境を調査・分析する試みが行われています。
今回の調査地は小瀬田・宮之浦・深川の3地区で,堆積環境はいずれも混濁流による海底扇状地と推定されます。宮之浦地区では化石の並びが南北方向に定まっており,当時の水流の向きとの一致が確認されました。また,小瀬田地区ではTerebellinaにU字管状の構造が認められ,曲率や管の横幅の変化から,巣穴の復元図も示されています。発見された生痕化石と,化石ができた環境の分析から得られた知見は,堆積環境や古生物の生態解明における貴重な資料となっています。
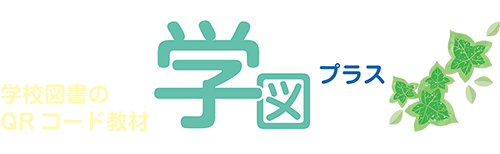
×
0 results
| URL | 文章 |
|---|