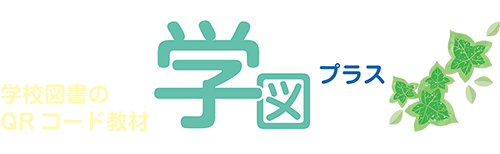今年も厳しい残暑が続いています。もう少しだけ夏の話題ということで,蚊についての研究成果を追加で1点です。
蚊のもたらす害をおさえるためには,蚊の個体数を減らす取り組みが直接的かつ効果的です。蚊は有性生殖を行う動物であるので,メスとオスの個体が出会う頻度を減らすことができれば,繁殖の機会も減り,個体数の抑制につながると考えられます。
日本でいわゆる『ヤブ蚊』とよばれているネッタイシマカは,デング熱やジカ熱といった非常に危険な病気を媒介する蚊の一種です。この蚊は,オスがメスを認識するとき,メスが発する羽音で生じる空気の振動に合わせてオスが触覚を能動的にふるわせることで,効率よく羽音を受け取り,すみやかにメスの個体のもとへ向かう行動をとることが知られています。
名古屋大学の研究グループは,ネッタイシマカのオスがメスの羽音を鋭敏に検知する聴覚機能について,神経内で情報を伝達するオクトパミンと,細胞内ではたらくcAMPという物質が関与していることを明らかにしました。これらの物質のはたらきを実験的に調節することで,聴覚器のはたらきが変化することが確認され,蚊の聴覚が化学物質を介して柔軟に制御されていることが示されました。
この研究成果は,蚊の聴覚を標的とした,繁殖行動に対する新たな防除戦略の開発に貢献する可能性があります。また,聴覚器の調節にはたらく物質を受け取る遺伝子の構造は蚊の種によって異なることも判明しており,今後の進化的,および機能的な研究が期待されています。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)