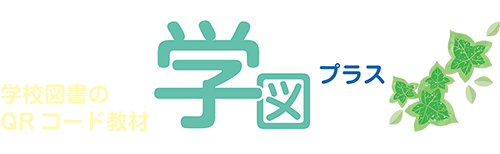地球規模での喫緊の環境問題となっているマイクロプラスチック。この問題に対し,野外で自然に分解されることで環境への影響を低減する生分解性プラスチックは,解決策のひとつとなり得ますが,よくよく考えてみると,”使用時のじょうぶさ”と”使用後の分解されやすさ”という,相反する2つの性質を両立する必要があることに気がつくでしょうか?
リサイクルの容易なプラスチックの原料となるポリマー(プラスチックを構成する単位)には,ポリマーの構成単位となるモノマー間が比較的弱い結合によって結びついた,高い分解性を示す「超分子ポリマー」とよばれるものがありますが,この高い分解性がゆえに,これまで超分子ポリマーは,柔らかい材料にしか使えず,一般的なプラスチックの代替はできないと考えられてきました。
今回,この欠点を補うように作製されたのが,2種類のモノマーを特殊な架橋構造で結合させて得られた,ガラス状の超分子プラスチックという新素材です。この素材は,耐熱性や硬度などの条件に対し,既存のプラスチックと遜色がない物性を示すことがわかりました。その一方で,ひとたび海水のような塩水に入れると,取りこんだ生物が代謝可能なレベルとなるまですみやかに分解されるため,マイクロプラスチックは形成されません。さらに,いったん分解されても,エタノールを使って容易に回収でき,また,回収後は超分子プラスチックへと戻すことが可能です。つまり,撥水被膜で覆って塩水への耐性をもたせるだけで,水中をふくむさまざまな野外環境で長期に,安全に使用することができます。
この盛りだくさんな利点をもつ超分子プラスチックは,これからのプラスチックのあるべき姿を示すと考えられます。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)