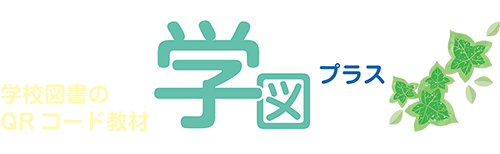食べ物を飲み込む過程には複雑なメカニズムが関与しており,超高齢化が取りざたされている日本においては特に,加齢や病気による誤嚥(ごえん)のリスク管理は重要な問題となっています。液体は流れが速く誤嚥しやすいため,”とろみ”をつけることで飲み込みのタイミングを調整できます。しかし,ではどのくらいとろみをつけるとよいか?という点については,食事提供者の感覚に依存する部分が大きく,適切なとろみの客観的な基準はこれまで十分に研究されていませんでした。
北海道大学の研究チームは,「流速分布計測支援型レオメトリ(VPAR)」とよばれる機器を用いて,お粥の流動特性を詳細に解析しました。その結果,お粥の種類のうち,白粥の粘度が最も高く,小豆粥はやや低く,玉子粥は最もさらっと流れることが判明しました。またすべてのお粥は,かき混ぜたり,力を加えたりすると粘度が低下する性質をもっていることもわかり,嚥下の観点から優れた食品であることを再確認する結果となりました。
この研究の成果をもとに,嚥下障害を抱える人々にとっての安全な食事設計が科学的なデータにもとづいて最適化できるようになり,さらに,流動食品への応用も期待されます。科学的な裏付けのある適切な”とろみ”は,高齢者や病気を抱える人々のQOL向上に寄与することでしょう。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)