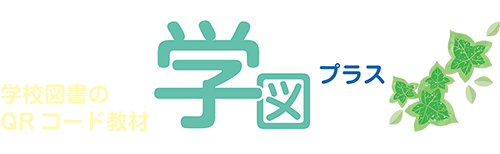花の間を飛び回って花粉や蜜を得ている,ミツバチやマルハナバチなどのハチのなかまは,効率よく花を訪れるため,視覚を活用した飛行ルートを構築することが知られています。仏エクス=マルセイユ大学の研究チームは,そんなミツバチの飛行能力を試すため,長さ220cmの長方形のトンネルを用いて実験を行いました。ふつうに飛ぶならミツバチにとっては造作もない距離ですが,実はこのトンネルには仕掛けがあり,天井と床をそれぞれ,通常の壁面/鏡面で切り替えられるようにしてあります。また,トンネルの出口にはエサが置いてあるため,ハチはそれを目指して,出口めがけて飛ぶこととなります。この人工的な環境でハチを飛行させ,視覚情報の変化が飛行におよぼす影響を調査しました。
実験では,天井と床の両方を通常の壁面とした場合と,天井のみを鏡面とした場合のどちらも,ミツバチは問題なくトンネル内の飛行を継続することができました。これに対し,床のみを鏡面にした場合,ハチはうまく飛べなくなってしまい,40cmほど飛んだあと,鏡の床に墜落してしまうようになりました。さらに,天井・床の両方を鏡にして,体感上の高さを無限とした場合,なんとわずか8cm飛んだだけで墜落してしまいました。
これらの結果に対し,研究チームは,ミツバチは腹側(地上方向)にある視覚的サインを利用して安定した高度維持をしている,と結論付けています。実はこのような現象は,われわれ人間にも起こるもので,航空機のパイロットが雲や濃霧中で視覚的手がかりを失ってバランスを保てなくなる,「空間識失調」とよばれる状態と類似しています。しかしその一方で,ハエの一種であるミバエで同様の実験を行ったところ,墜落は発生しませんでした。生物の種類によって,飛行維持の技術に共通性と多様性が見られることは興味深い結果といえます。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)