物質の状態は,気体・液体・固体の3態に分類できることは,1学年で習う化学の基本です。それぞれの状態のときの物質を構成する粒子のミクロなふるまいは,教科書でもくわしく解説されているのでイメージしやすいかと思うのですが,改めて考えてみると,物質を肉眼のスケールで観察するときの3態の明確なちがいは,具体的な説明が難しいことに気がつくと思います。特に,ゼリーやスライムのようなものも存在する,液体と固体の明確なちがいはどこにあるのでしょうか?
実は,固体と液体は明確に分けられるわけではなく,観察する時間スケールや外からの力によって変化する,というのが,この問いへのひとつの解答となります。固体は分子間の結合が強く,形を保持する力が強いのに対し,液体は分子間の結合が弱く,自由に流動します。しかし,ガラスやアスファルトなどの物質は,長期間ではわずかに流動する性質をもつため,絶対的な固体とは言えません。このような特徴を研究するのが「流動学」という学問分野であり,この分野では,物質のねばりけや弾性を分析し,固体と液体の中間的な性質の評価を行います。
この視点から,『猫は液体か?』というユーモラスな問いが科学的に分析されました。フランスの物理学者ファルダンは,猫のリラックス時間(形を変えて落ち着くまでにかかる時間)を流動学でいうところの緩和時間とみなし,観察時間と比較して計算したところ,猫は液体と解釈できるふるまいをする,という結論が得られました。すなわち,導き出された結論は,“猫は状況次第で,液体としても固体としてもふるまう性質をもっている”となります。ファルダン氏の研究は,このユーモラスな着眼点と議論の正当性が評価され,2017年にイグノーベル賞を受賞しました。
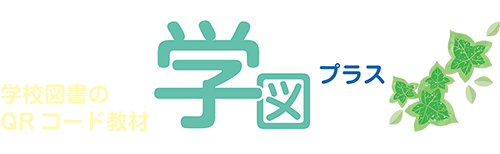
×
0 results
| URL | 文章 |
|---|