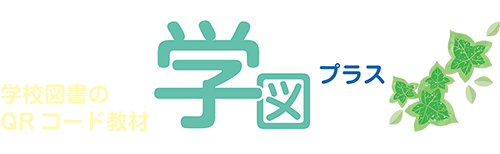金属の「さび」は,教科書にも掲載されている,おだやかに進行する酸化現象のひとつです(2学年p.15)。さびが進行すると,もともとの金属とは異なる酸化物ができるため,変色したりもろくなったりしてしまいますが,世界にはなんと約1600年もの間,さびに耐えている鉄柱があるというから驚きです。
インドのニューデリーにあるクトゥブ・ミナール遺跡群には,高さ7.2m,重さ6トンの大きな鉄柱が立てられています。この鉄柱の起源は5世紀にまでさかのぼるとされていますが,特筆すべきは,屋外で風雨にさらされながら,建築当初から鉄柱としての原型を保ち続けていることです。
この耐久性の謎は,古くから科学者の関心を集めてきており,研究は1912年から始められていましたが,結論が出たのは100年近く経過してからの2003年となりました。インド工科大学の研究者らの発表によると,製鉄のなかでもさびにくい性質をもつ錬鉄(れんてつ:炭素をあまりふくまない鉄)を素材としており,加えて,一般的な鉄と比較すると,リンを多くふくむ一方で,硫黄とマグネシウムが少ないことがわかりました。リンが多くふくまれる金属は,さびに強くなることが知られています。また,「鍛接(たんせつ)」とよばれる,現代ではめずらしい技法が使われていることも判明しました。この技法は,金属どうしをとかさずに,固体のまま加熱・加圧して接着するもので,この技法を使うことで,リンが多くふくまれたまま加工ができた点が指摘されています。さらに,柱の表面には,鉄・酸素・水素で形成された化合物のうすい層ができており,この層がさびへの耐久性をさらに高めたことも考察されています。
当然,5世紀当時にはこのような化学的な性質はまったくわかっていなかったのですが,経験をもとに職人たちがこのような人工物をつくり上げたことは本当に圧巻です。その創意工夫に敬意を表して,研究チームではこの柱を“古代インドの冶金※技術の生きた証し”と表現しています。
※冶金(やきん)…金属を鉱石などから取り出し,精製・加工して,実用可能な金属材料をつくり上げること。
もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)