寒い火星をあたたかく
他の星を地球に似た環境に人工的につくり変えることを,テラフォーミングといいます。太陽系の隣の惑星である火星は,テラフォーミングの最有力候補とされていますが,現時点では人類の居住には適していません。これは,火星の平均気温が …
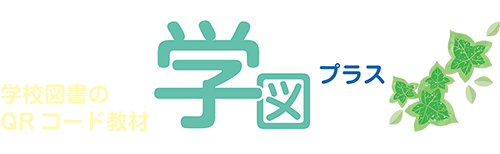
他の星を地球に似た環境に人工的につくり変えることを,テラフォーミングといいます。太陽系の隣の惑星である火星は,テラフォーミングの最有力候補とされていますが,現時点では人類の居住には適していません。これは,火星の平均気温が …
磁石の同じ極どうしの間にはしりぞけ合う磁力がはたらき,たがいに反発することは,おもちゃからリニアモーターカーにまで利用される身近な現象です。これをうまく利用すると,下側からの磁力によって,上側の磁石を浮かび上がらせること …
花の間を飛び回って花粉や蜜を得ている,ミツバチやマルハナバチなどのハチのなかまは,効率よく花を訪れるため,視覚を活用した飛行ルートを構築することが知られています。仏エクス=マルセイユ大学の研究チームは,そんなミツバチの飛 …
北極の海氷面積は,毎年3月ごろにその年で一番大きくなるというサイクルをもっています。2025年も,3月20日に,その面積が年間最大の1379万km²に達しましたが,この値は衛星観測が始まって以来の最小記録となりました。こ …
物体が落下するとき,重いか軽いかにかかわらず落下する速さが同じになることは,教科書にも掲載されている有名な現象です(3学年p.245)。落下する物体の重さと速さの関係は,16世紀にガリレオ・ガリレイによって実験的に確かめ …
コインを投げる(コイントスをする)とき,表が出るか,裏が出るかの確率は,どちらも50%である―これは中学校段階でもよく目にする,確率の最も基本的な事例です。しかし実物のコインは,刻印や厚さなどの影響により,表面と裏面とで …
たとえば,近所のスーパーに買い物に行き,食品を見るだけで,産地や消費期限,オススメの調理法までもが一緒に視界に映る…。こんな世界も,スマートコンタクトレンズを組み合わせた拡張現実(AR)技術の発展により,夢物語ではなくな …
名古屋大学の研究チームは,白髪の原因とされる,メラノサイト幹細胞の減少や老化という現象に着目し,セロリやブロッコリーなどの野菜にふくまれる物質である「ルテオリン」の白髪抑制効果を調べました。 研究には,体毛が通常より早く …
食べ物を飲み込む過程には複雑なメカニズムが関与しており,超高齢化が取りざたされている日本においては特に,加齢や病気による誤嚥(ごえん)のリスク管理は重要な問題となっています。液体は流れが速く誤嚥しやすいため,”とろみ”を …
地球規模での喫緊の環境問題となっているマイクロプラスチック。この問題に対し,野外で自然に分解されることで環境への影響を低減する生分解性プラスチックは,解決策のひとつとなり得ますが,よくよく考えてみると,”使用時のじょうぶ …
読み取り中...